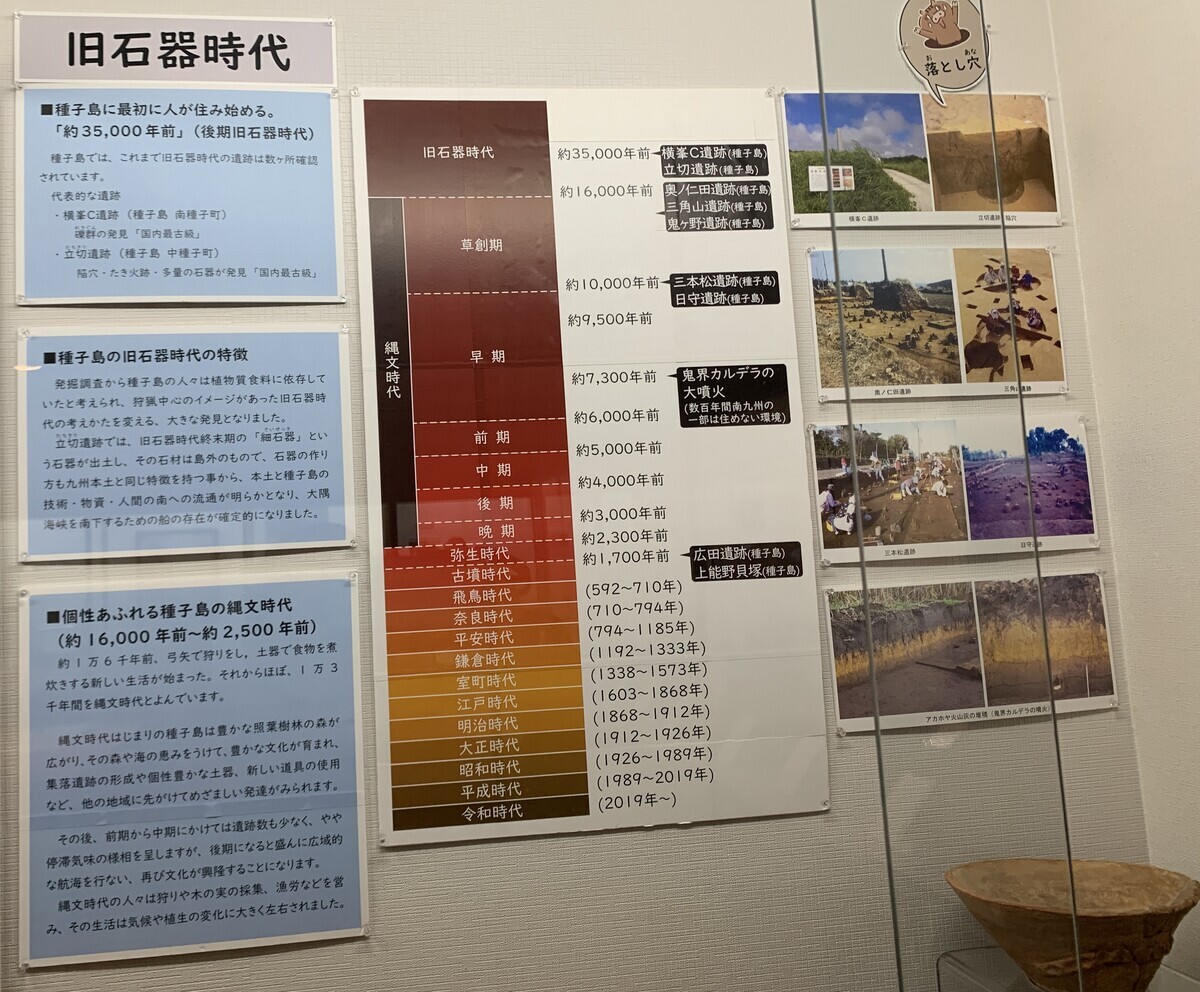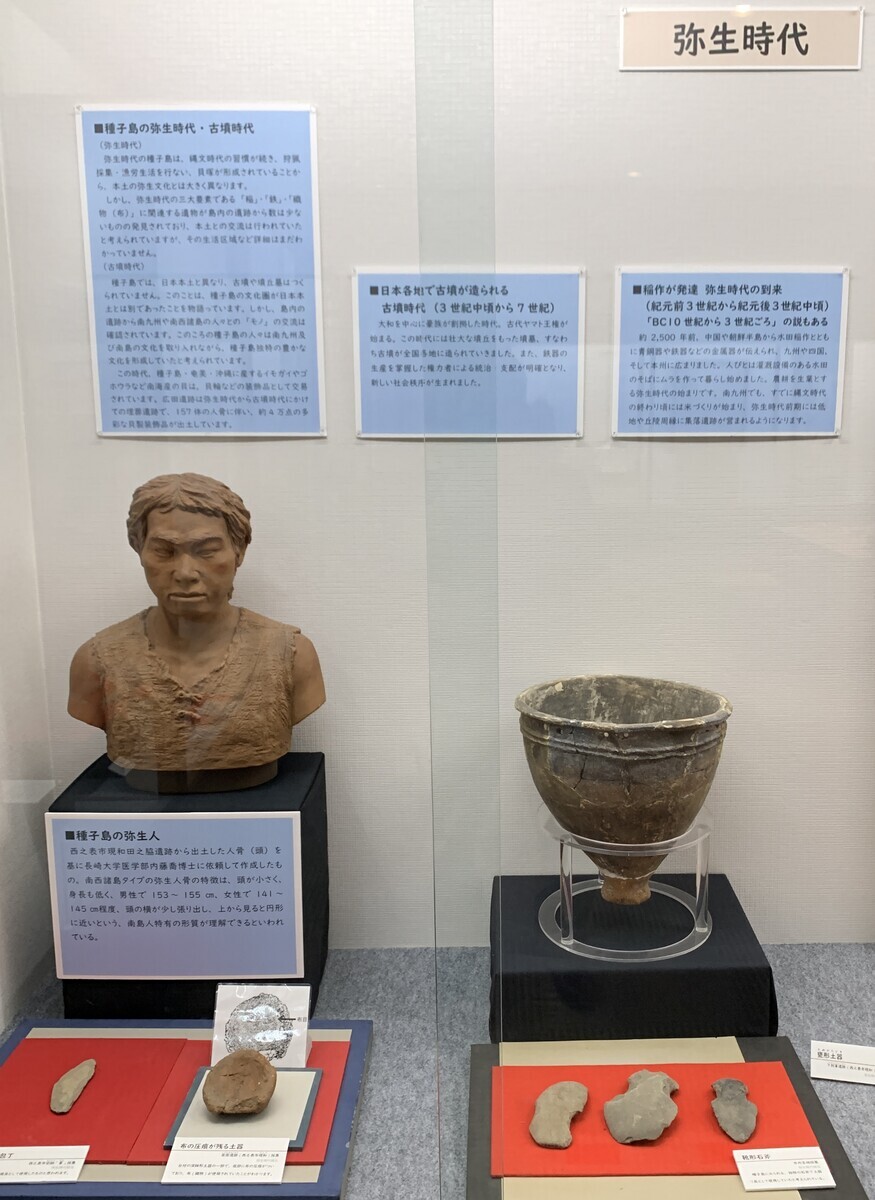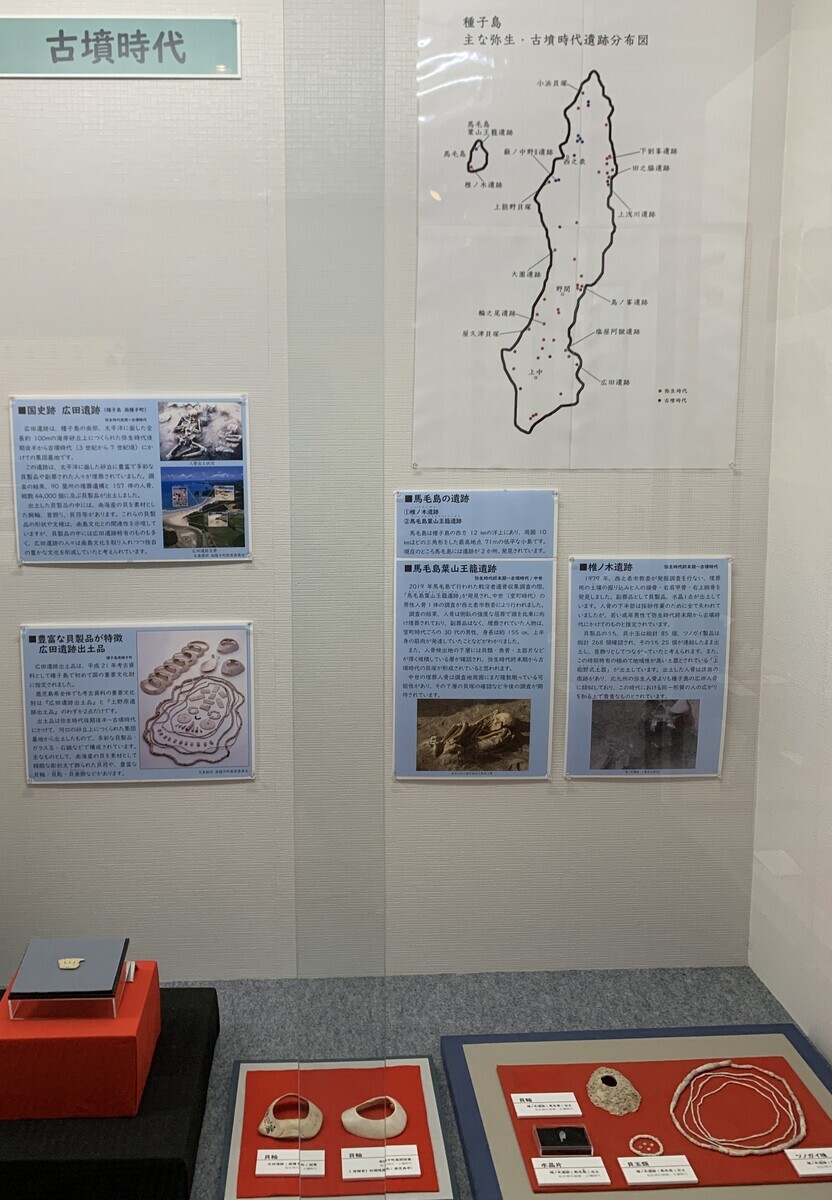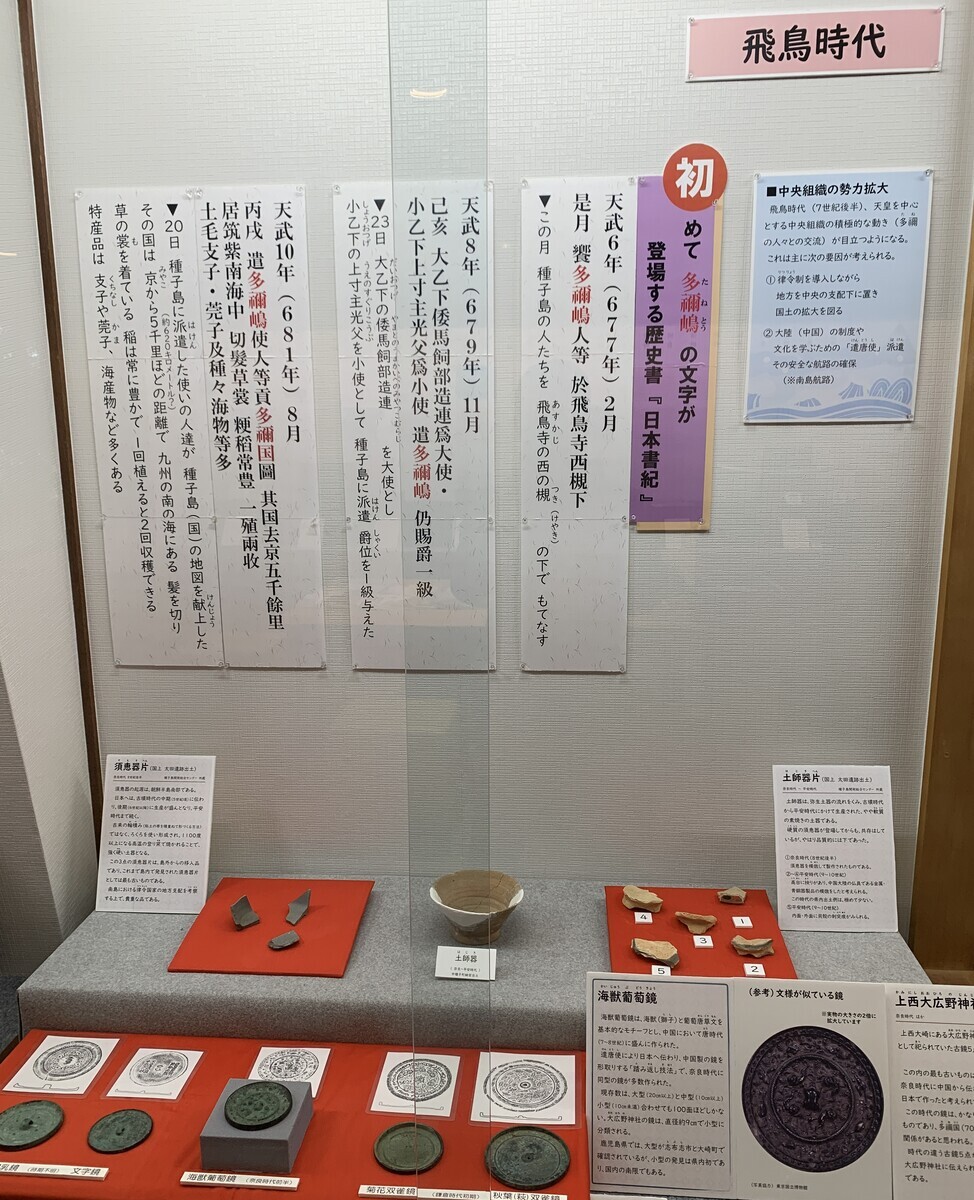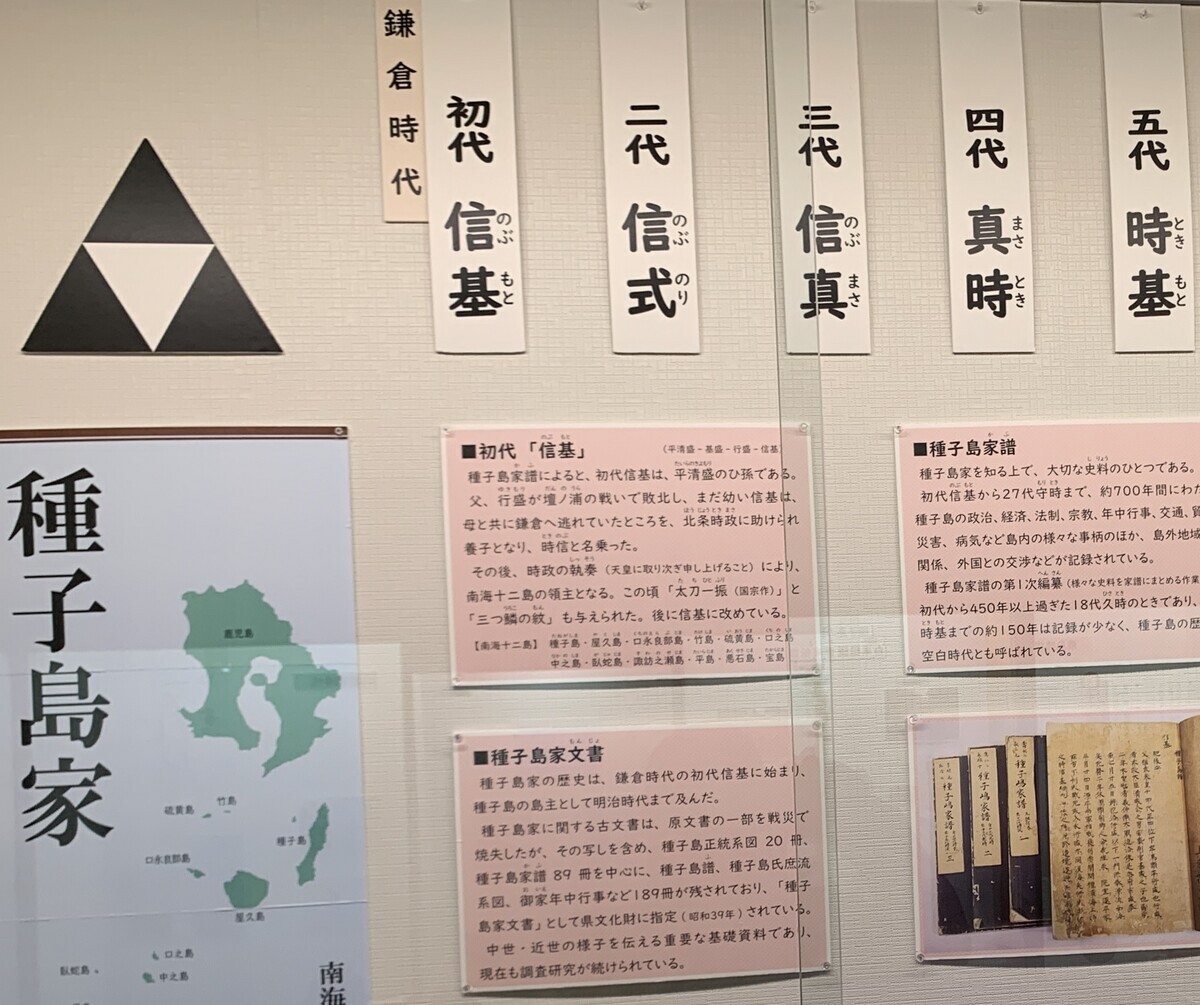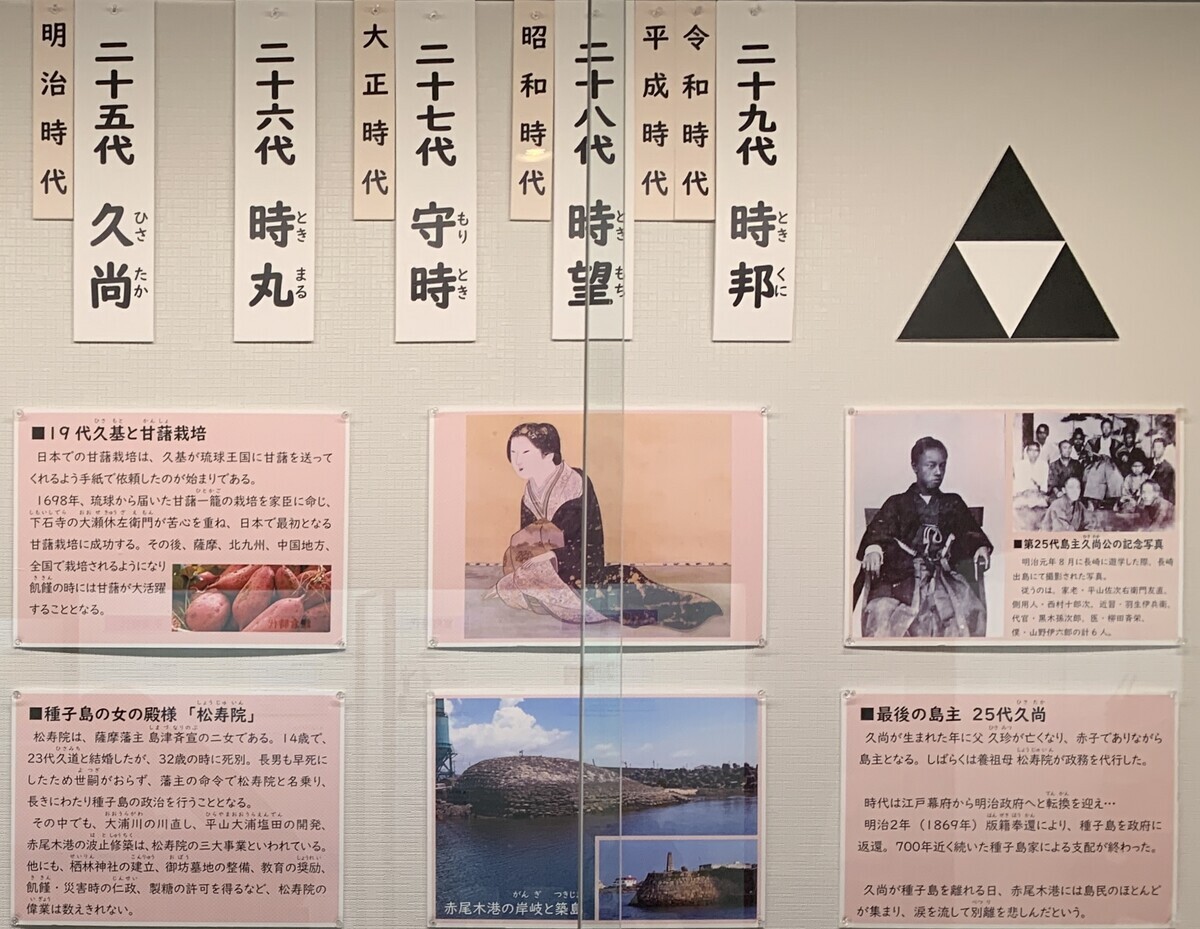市に譲渡された現在では、当時の面影が残されたまま、月窓亭として一般公開された。季節ごとにひな祭りや、端午の節句など、昔ながらの年中行事を再現した展示を行っている。種子島のひな祭りは、女の子が誕生して初めての節句の日、夜に親類縁者がやってくる。ダーに花や餅で飾ったお膳を持って集まってくる。床の間には土人形が飾られ、ダーが並べられる。ダーは大根を10センチほど切ったものを置き、季節ごとの花を差して飾る。周囲には紅白の丸餅、緑色の蓬餅などが添えられる。ダーとは台(お膳)のことである。このような光景は大正時代まで続いたが、現在では見られない。

入館するとまずは月窓茶(月桃茶)と種子島の食材を使ったお茶菓子を出してもらえる。月桃茶は、ポリフェノールを非常に多く含み、独特の香りとほのかな甘味は清涼感があり、リラックス効果抜群という。抗菌作用が強いので葉っぱで餅や肉を包んだり、油を絞ってアロマオイルにしたり、虫除けに使ったりする。

庭には月桃も植えられている。月桃はショウガ科の多年草の薬用植物で、熱帯から亜熱帯のアジアに分布し、種子島、佐多岬が自生北限とされる。6月ごろに桃に似た色合いの花の蕾をつけるのが、月桃の名前の由来である。種子島の人々は、月桃のことをシャニンやサネンと呼んでいる。

月窓亭の中庭や庭園など敷地内に自生している植物は、その数なんと300種以上という。絶滅危惧種だけでも20種類もあるそうだ。小さな池の向こうには大型シダの一種ヘゴが植えられている。種子島にはこの亜熱帯に生息するヘゴが、約7万平方メートルにわたって自生している。手前の池ぎわに生えているのは、観葉植物のモンステラ。茎は太く羽状に大きく切れ込んだ葉が特徴。大きく育つと白い仏炎苞と緑色の肉穂花序をつけた花を咲かせる。三本の肉穂花序が認められる。果肉はバナナとパイナップルを合わせたような味で美味しいという。

こちらはミツバウツギ科ツルビニア属のショウベンの木。面白い和名は、春先に枝を切ると切り口から臭気の強い樹液が大量に出ることからつけられたという。四国南部、九州から沖縄にかけて分布する。

こちらはサトイモ科クワズイモ属のクワズイモ。四国南部、九州以南の奄美・沖縄群島に分布する。奄美・沖縄群島では道端や林などに広く自生している。食べられないだけでなく、毒草であり、中毒事故に注意が必要である。


こちらはよく観葉植物で見かけるポインセチア。原産がメキシコと中央アメリカの常緑性低木。標準和名はショウジョウボクで、ポインセチアは通称である。観葉植物としては短日処理を行い、クリスマスの時期に合わせて紅葉させ、緑色の葉とのコントラストを楽しむ。

こちらの淡い藤色の花は、園芸植物のテトラデニア(Tetradenia riparia)という。南アフリカ原産の非耐寒性の多年草低木で、日本には明治末期に渡来したという。和名はフブキバナ(吹雪花)というが、花色は白または淡紫色を帯びる。